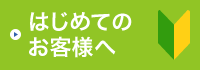いつもネジクルをご利用いただきありがとうございます。
ネジクルの視点【2025/08/06-394号】
2025年8月5日に公開された電通総研と電通による共同調査「新たな事業創出とR&Dの関係性に関する調査」では、日本企業の研究開発部門と新規事業創出との間にある“ねじれ”構造が明らかになりました。特に「R&D部門は存在しているのに、事業創出には結びついていない」という企業が多数派を占めており、日本の産業競争力の源泉に一石を投じる内容となっています。
1. R&Dの存在はあるが事業化につながらない企業が過半数
調査によれば、R&D部門が存在しているにも関わらず、新規事業の立ち上げには直結していない企業が63.6%にも上ることが分かりました。これは、R&D活動が既存事業の延長線上にとどまり、破壊的イノベーションには至っていない現状を示しています。
2. “探索型R&D”を担う部門の希薄さ
新規事業に寄与する“探索型R&D”を担当する専任組織がある企業はわずか16.4%。また、その探索R&Dが事業部門と接続されているケースはさらに限定的であり、研究成果のビジネス化が難航している現状が浮き彫りになりました。
3. 研究者自身も「事業化に結びつかない」と自覚
R&D従事者へのアンケートでは、半数以上が「自分たちの研究は新規事業創出にほとんど貢献していない」と認識しています。これは企業風土や評価指標の偏りが、挑戦的な研究や成果の事業化を妨げている可能性を示唆します。
4. 成功事例に共通する“接続性”と“推進者”の存在
一方で、新規事業に成功している企業の多くでは、「研究と事業開発の橋渡しを担う人材」や「経営直下の新規事業推進体制」が存在しており、部門間のスムーズな接続が成果につながっていることが分かります。
5. 日本企業の生産財・BtoB領域における変革の兆し
今回の調査対象には製造業も多く含まれており、「基盤技術からの事業転用」「製品単体から価値提供への転換」など、ネジクルのようなBtoB取引を行う企業にとってもヒントとなる構造変化が読み取れます。
ネジクル解説コメント
1. 製造業における“価値連結型”の取引が重要に
ネジクルでは、単なる部品供給ではなく「最適納期」「1本対応」「検索性の高さ」といった“価値”を取引の中心に据えています。これは、今回の調査で指摘された“R&D成果を顧客価値へ変換できていない”という課題への対応そのものです。
2. 技術者と営業の接続を生む“ECプラットフォーム”の可能性
研究者と現場の距離を埋めるには、技術者の想定を超えた現場ニーズを即座に収集・反映できる場が不可欠です。ネジクルのような高速・高精度の検索が可能なECは、現場の声を可視化し、設計・開発へフィードバックをかける仕組みの一端を担います。
3. ネジ一つから始まる“事業創出の現場主導”
「このネジ1本がすぐ届く」ことが、ある製品の量産可否や顧客納期の維持に直結します。このような視点が研究・R&Dに逆流していくことで、現場起点の探索型事業創出が活性化すると、ネジクルは考えています。
・詳細はこちら
https://www.dentsusoken.com/news/release/2025/0805.html
【記事に関連する商品情報】
- 座金組込ねじ(ワッシャー一体型)
→ R&Dと量産現場の橋渡しに不可欠な“組付け性”向上製品です。 - タッピングネジ1種 なべ
→ 樹脂や薄板への対応など、新素材開発と連動する多用途モデル。 - 樹脂用ねじ(先端特殊形状)
→ 研究・試作段階から多く使用される製品で、研究用途に適応。 - 鉄製 六角ボルト(ユニクロメッキ)
→ 量産ラインで最も使われる標準部品。標準品の供給安定性が事業創出の基盤。 - 特殊ねじ(切削加工・少量対応)
→ 探索型R&Dに必要な一点物対応可能なラインナップ。
SNSでも最新情報発信中!
X(旧Twitter):https://x.com/nejikuru
Facebook:https://www.facebook.com/nejilog
LinkedIn:https://linkedin.com/company/tsurugacorp